町中、どこでも「冒険」。そんな町になったらいいなと思っています

原田児童館解放ゲーム大会
-お忙しいところインタビューをお引き受けくださり、ありがとうございます!
老舗珈琲店の「萩原珈琲」代表としての萩原さんのお話はあとで詳しく聞かせていただくとして、まずは地元でのいろいろな活動についてお聞かせいただけませんか。
いつも楽しそうな活動をInstagramにアップされているのを、私、実はこっそりフォローして拝見しているもので…(笑)!
フォローしていただいているのですか、ありがとうございます。
「祭り」があればそれをきっかけに地域の皆が世代問わず集まるきっかけになるのでしょうが、私がいるこの地域(神戸市灘区・原田)は、「祭り」のない地域です。
だから、多世代が集うきっかけになるものを発信できたらいいなと思って動いています。
「町の活性化」とはよく言われていますけれど、僕が思っているのはちょっと違っています。活性化しよう!と気負って動くのではなく、町のいろいろな要素や場所を、ごくシンプルに、ごく自然な形で活用した結果、町のお年寄りから子どもまでが楽しい町になっている・・みたいなのが理想です。
新たなこと、大きなことをするのではなく、シンプルなイベントばかりです。
-多世代が集うきっかけのイベント。たとえばどのようなものでしょうか。
子どものためのイベントって、得てして子どもだけにフォーカスしがちだと思うのですが、僕は60代、70代の方々にも参加していただく前提でプランニングします。
イベントの内容としてはシンプルで、もともとある物を利用する。
雨の日ならその雨を利用して、「雨に濡れる楽しいこと」をする。
たとえば来る3月28日には、「森の音楽会」というものを実施する予定です。
これはいろいろな木や石で楽器を作って、奏でてみようというイベントです。
紙飛行機も作って飛ばしてみよう!というのと、自作の楽器を使い、紙飛行機が飛ぶ様子を音で表現してみよう!を一緒にできたらいいなと思います。
「そんな行き当たりばったりで大丈夫?音源や楽譜は用意しなくてもいいの?」という声もあるでしょうが、固定概念は取っ払いたいです。
お手伝いというか、企画側のメンバーに関しても、「何かやりたいけれど関わるきっかけがない」という人たちがいると思うので、イベントをすることでそのきっかけになれたらという想いもあります。
森の音楽会のアナウンスにも、「紙飛行機の達人を探しています!」と載せたのです。
もしかしたら、「あ!僕、紙飛行機なら得意ですよ!」という人が参加してくれるかもしれないと考えました。
若手青年プレーヤー(実行委員)を発掘!と大々的に動くのではなくて、小さいことを重ねて、気が付いたら結果的にたくさんの人たちが楽しんでいる...こんなスキームでやっています。
あとは、なんでもゲーム感覚にしちゃえ~!というかんじで。
ボランティアって、自分が楽しまないと。
子どもたちだけじゃない、実はおじちゃん・おばちゃんたちの方がやる気あったりします。
世代を問わず、どんどん力を合わせれば、いろいろ実現可能です。
ごみ拾いレースをやろう!という企画のときは、集めたごみの総重量で勝敗を決めました。
景品は、廃材で作ったものをプレゼントしました。
その時にしかもらえないものを景品にしたいなと思ったのです。
子どもたちが大きくなって、その景品を見た時に、「なんやこれ?!あぁ、そういえば昔こんなイベントに参加したなぁ!」と思ってくれたら嬉しいです。
あえてアナログにいく。アナログを武器にする。そんな感じでやっています。
-おっしゃる通りです。
気負わず、地道なことの積み重ねが、その結果として町のみんなの楽しみや思い出に繋がればいいですよね。
ところで過日、税務署のお仕事もされているような投稿も拝見しました。
仕事といいますか、税金とはなにか?ということを子どもたちにわかりやすく教えるという命を受けました。
税金の授業って、ビデオを見せたりするのが主流みたいなのですが、僕はそんなものじゃこどもたちに響かないと思って、はりきってパワーポイントで資料を作成しました。
生まれてからこんな場面でこんな税金を払っていますよ、あなたたちが18歳になったらこんな税金を払わなくてはなりませんよ、・・・って、ポンポンとポップアップするものです。
税務署の人にひかれたかもしれません(笑)。
これからも楽しくわかりやすく伝えていくお手伝いができたらいいなと思っています。
-今の萩原さんのいろいろな活動、その原点は。
小さいころの記憶でしょうか。
市場がありまして、学校の帰りに、そこを通り抜けるだけでおじちゃんおばちゃんに十数回は声をかけられていました。
今でもそのおじちゃんおばちゃんたちの顔を鮮明に覚えていますよ。じゃんけんをして勝ったら飴ちゃんをもらったり。
そういう町が面白いと思うんです。
町中、どこでも「冒険」。
僕の考えに賛同してくれるメンバーが一人、また一人…と増えて、今に至ります。
入学時、担任の先生の言葉に衝撃を受けました

治安・景観維持のための麻袋プランター設置(手前の緑のズボンの男性が萩原さん)
-詳しくありがとうございました!
さて、それでは神戸高校時代のお話に…。 神戸高校を志望された理由はありましたか。中学生の時、頭だけは良かったので、神戸高校に入りました。
神戸高校に入って何かがしたい、という想いがあったわけではなかったと記憶しています。
合格して、入学までに「自由と規律」の本を読んでおくようにという課題がでて、「え~難しそうな本やなぁ!」って。
高校での授業は一方的に先生が話して進んでいく感じでした。自分で予習しておかないとまったくついていけない。
とにかく大変でした。
部活は陸上部に所属して、その後キャプテンを務めました。
「走れないキャプテン」、「記録のない部長」と言われていました(笑)。
当時の仲間のうち、2~3人とは、今も連絡を取り合っていますよ。
-神戸高校で印象に残っていることはありますか。入学式当日だったでしょうか、担任の生物の先生が
「昨今、『地球の温暖化』ってみんな言っていますけれど、地球規模で見ると『氷河期』に入りますからねっ!!」とおっしゃったのが、強烈に印象に残っています。
小さな単位で物事を見るのではなく、大きな視野で見なくてはならないということをこの先生から入学時に教わったので、3年間そのように過ごしたのではないかなと思います。
あと、神戸高校は「討論」する機会がたくさんありました。
学年で、勝ち抜きのディベート大会も何度かやったのが印象深いです。
神戸高校生、個性が強い人が多くないですか?
学年内でのディベート大会を通して、いろいろな考え方を知ることで、物事を多角的に見る力がついた気がします。
社会に出てからも、「こういうとき、あいつならどうするだろう?」とか考えることがありますし、今になって、討論で鍛えた考え方が活かされていると感じます。
「質素剛健・自重自治」という学校の精神も、今となってはとても好きです。
あっ!
今では主流?となった、受験生にキットカット(きっと勝つ!にかけている)のチョコ、というのが流行り出した時期で、
まだキットカットのパッケージにメッセージ欄がなかった時代でしたけれど、高校3年生の時、仲間と学校に残って勉強もせずに「誰にキットカットを渡すか」ということをずっと考えていた記憶もあります。
-卒業後、「神戸高校OBで良かった」と思われることはありますか。そうですね、僕は自分が神戸高校卒業生であることに特段こだわりはないのですが、神戸高校卒業生のネットワークはすごいなと感じることがありますし、先輩方が気にかけてくださるのはありがたいです。
過日、
株式会社淡路屋の寺本督さん(32回生)がポートピアホテルでの食事に招いてくださって。
ご自身の会社もコロナで大打撃を受けておられるであろう中、後輩である僕たちを激励してくださいました。
ありがたかったです。
「昆虫」は面白い!!
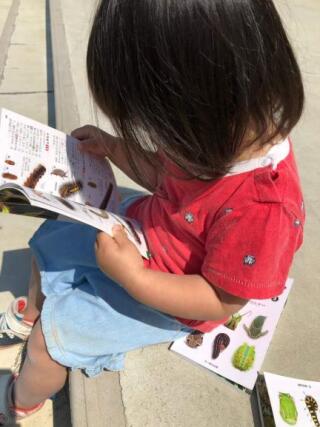
パパ譲りで毛虫が大好きな萩原さんの娘さん
-萩原さんの個人のInstagramでは、昆虫に関する記事もよく投稿されておられますね。
小学校4年生の時の先生がとても個性的な方でした。
今では考えられないことなのですが、2学期までに理科の教科書を全部終わって、3学期はひたすら課外活動!という先生で、飯盒のやり方を教えてくださったり、摩耶山に登ったり。そのおかげでしょうか、動物や自然がとても大好きになりました。
高校でも化学と生物を専攻し、大学ではその興味の延長で「昆虫」についての研究をしました。
生物界の被食・捕食の関係とか、知れば知るほど面白いですよ。
新種が見つかる速さも、絶滅する速さも面白い。
栄養が木から土に戻るのも昆虫のおかげ。
…そんなことを考えたら「昆虫」って奥が深いなって。
たとえば、毛虫って嫌がられること多いですけれど、葉っぱがひらひら地面に落ちるより、毛虫が葉っぱを食べてフンしたほうが、圧倒的に速くチッソ・リン・カリウムに戻るわけです。
という風に見ると昆虫の役割って偉大だし、「すべての原点は昆虫だ!」と思います。
でも大学のゼミでは外来種の蛾の生態系調査をやることになりました。若干自分がやりたかったこととは違いましたが、動物生態学とか統計学という点では、この時の研究が今も役立っています。
卒業後は単身ブラジルに渡り、そこからグアテマラにわたり、農園に住んでコーヒーについて学びました。もちろんポルトガル語とスペイン語もその時に習得しました。グアテマラでは「日系ブラジル人が来た」と間違われるほど、ポルトガル語なまりのスペイン語を話していました。その後、英語も必要だなということで、そのままシアトルに移って英語の勉強をしました。
今はもう、スペイン語は全然思い出せませんが。
帰国後は東京の食品会社に入社し、東京で結婚しました。
高校卒業後初めて、26歳の時に帰神しました。社会人になって会社で3年働いたら神戸に帰ってこようとは決めていましたから。
萩原珈琲に入社して、5年くらいかけて、製造から始まって全部署を経験しました。
中でも一番、商品企画開発が楽しかったです。
萩原珈琲で最初に取り組んだのは、老舗ならではの”曖昧な部分”をなくしたことでした

コーヒー染め、淹れ方講習での萩原さん@神戸市立自然の家
-萩原珈琲に入って、全部署を経験。
その後、代表取締役になられて、最初に着手されたことは。
東京で働いていた会社は、値段勝負というところがありました。一円、二円ではなく何十銭をいかにカットするかという世界でした。10銭の差でコンペで負けたこともありました。
対して萩原珈琲は、タイトにコストを詰めていくというよりは、自分たちのブランド力を高めて発揮すること、そのためにまずは「可視化」することに着手しなくてはと思いました。
もちろん自分の父や代々の代表者らをはじめとして、萩原珈琲を育ててきてくれたことは本当に尊敬しています。
一方で、老舗なので曖昧なことも多くありました。
僕が最初に取り組んだのは「萩原珈琲はこういう会社です」「萩原珈琲の商品は〇〇です」ときちんと言える”仕組み”づくりでした。
たとえば受注焙煎とほとんどやっていることは一緒だけれども、受注焙煎をしています!とは謡いにくかったんです。
「午前中焙煎分はお昼に詰めて、午後の発送。その残りと、昼からの焙煎分は翌朝の市内営業配達用です」
24時間以内に出荷されることに変わりはないので受注焙煎とほぼ変わらないから、「受注焙煎ですよ~」って言ってしまえば簡単なのですが、そうではなくて、自分たちのやっていることを消費者のみなさんにきちんと説明できる。言葉で可視化する。まずはそこから取り組んでいかねばと感じました。
それでも余る豆って出てきます。人気のない豆、4~5種類。
それは「焙煎後72時間過ぎたら出荷しません」、こう明言しましょう、と。
でも4日目の豆ってまだまだとてもおいしいですし、食品廃棄は僕たちの本意ではないので、直営店でマイバッグを持参してくださった方に特典として30グラムずつ無料でお配りしています。ガチャガチャみたいに、どの種類があたるかわからないっていうゲーム性も持たせつつ。脱プラ推進!エコ志向の促進!と気負うのではなくて、消費者の方に楽しんでいただく結果、そう(脱プラ・エコ志向)になっている…という仕組みを確立できた気がしています。
手づくりならではの生産効率の悪さをあえて公開しています

本社直売所(神戸市灘区)
―御社のInstagramも、面白かったり、粋だったりで、レトロなかんじだったりで、毎回とても楽しく読ませていただいてます。
情報の発信という面でも、消費者に「見える」企業、というのを意識されているのでしょうか。
コーヒー屋のInstagramって、大体が「〇〇農園から豆が来ました~!」「コーヒーの淹れ方は・・」「この豆にはこんな特徴があります!」というような投稿が多いと思います。弊社のInstagramではそういうことはほとんど載せません。
むしろ、老舗だから、この会社規模だからできることとして、ほかとは違った「人間らしさ」「ほんまに手作りなんです」をウリにしていくために、内部の取り組みや作業風景を敢えてInstagramで発信したりしています。
ホームページでも、今まで㊙だった工場内部の様子を動画で初公開しています。本当に職人がいて、手作りでやっていますということを可視化しています。
ひと窯ひと窯、焼きあがるまで、焙煎士がずっと見ておかなければなりません。
今5種類の炭をつかっているのですが、その日の気温や・湿度を鑑みつつ焙煎士が自分で切って使用しています。
それでいて、焼き具合・仕上がりは毎回同じでないといけない、あるいは日によってのばらつきをほとんどないようにしなければならない。それが焙煎技術といわれるものです。
こういった手づくりならではの生産効率の悪さこそが、老舗らしくていいなと思っているので、あえて発信しています。
会社をどんどん大きくするというよりは、コンパクトに、もっと強い会社になりたいです。
でも一方で、以前のいいところを活かしながら、時代の流れや環境に適応して、必要な変化やチャレンジは恐れたくないと思っています。
たとえば、ECサイトを立ち上げたり、神戸市の制度を使った「副業雇用」もしたりしています。
東京の大手IT会社のマーケティング部門の人を、弊社で副業契約(業務委託契約)しています。おそらく弊社が、この神戸市の制度を使った初めての企業ではないでしょうか。
労働環境もだいぶ整えました。社員一人あたりの残業は平均6分/月、です。
完全週休2日制で、土日祝は全部休み。有休消化率は全社員7割を越えています。
子育てしている世代が多いので、そのあたりの社内環境を整えることも実施しました。
私自身、先日6人目の子どもが生まれて、子育て世代ですから、自分だったらこういう環境だと働きやすいな…と、比較的考えやすかったです。
20年後の自分への手紙

エコバッグを持つ萩原さん
-53回生と言えば、3年6組で卒業時に書いた「20年後の自分へ」のお手紙のお話、ロマンティックですね~!
同窓会公式Facebookでも紹介させていただきました。
萩原さんは3年6組でいらしたとか。3月27日にそのお手紙を担任の先生から受けとられるセレモニー?があるそうですね!
担任の先生にとって、僕たちが初めての卒業生だったのだと思います。
卒業時に20年後の自分にあてて書いた手紙を先生がずっと保管してくださっていて、20年後にあたる今年、渡しますということだったのですが、コロナで延期になりました。
でも延期の連絡がまわっていなくて、間違えて学校に来る生徒がいては大変と、先生が当日神戸高校の正門前で待機していると聞いたので、子どもたちと校門前まで会いに行きました。
恩師に子どもたちを会わせることができて、良かったです!
3月27日はどれくらいの級友が集まるか楽しみです。
-萩原さんが書かれた「20年後の自分への手紙」の内容。
またこっそり教えてくださいね(笑)。
長い時間、お話をお聞かせくださってありがとうございました。今後の益々のご活躍をお祈りしています!

